2009年07月05日
茶室のエレメント
まっさんです。
昨日は茶室の云われについてレポートしました。
今日は、その茶室にあるエレメントについてレポートします。
まず、茶室への入り口です。普通の家のように、玄関があるわけではありま
せん。
この入口の事を「にじり口」といいます。幅1尺9寸5分、約60㎝位です。
高さは2尺2寸5分ですから、65~70㎝位でしょうか。
とっても小さい入口ですね。
多分、私の巨体(身長:170㎝、体重:86kg、ウエスト:95㎝)では、き
っと入れるか不安です。
最も、偉い人専門に設けられた入口もあるのです。この入口の事を、「貴人
口」(きにんぐち)といいます。
中に入ると、目に付くのは、風炉(ふろ)です。ここで、お湯を沸かします。
周りを見渡すと、床の間があります。ひどく小さなスペースですが、床柱は
面皮柱(めんがわばしら)で、内面の柱や天井の縁は壁で隠されています。
この様式を「室床」(むろどこ)といいます。
畳が敷かれていますが、普通のものよりかなり小さいサイズです。この畳の
事を「台目畳」(だいめだたみ)といいます。
壁は土壁で、下地の格子状の竹を見せた窓があります。この窓を「下地窓」
(したじまど)といいます。そしてこの窓に引っかけておく障子を「掛け障
子」といいます。天井は、傾斜天井と平天井を組み合わせた掛け込み天井で
す。よしず貼り天井なども考案されています。私はこの天井が気に入ってい
ます。
最後に、茶を飲んでにじり口から、よっこら出たところに雪隠(せっちん)
やつくばい、石灯篭などが配されました。
雪隠とは便所の事で、つくばいは手を洗う場所のことです。
皆さん、思ったより一杯のエレメントが、この小さな空間を構成しているこ
とに驚かされますよね。
今日はここまで。
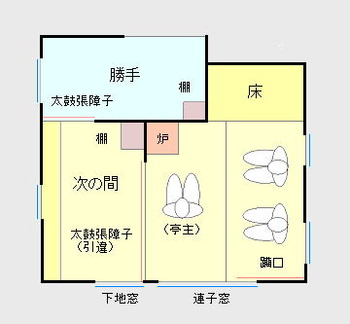
昨日は茶室の云われについてレポートしました。
今日は、その茶室にあるエレメントについてレポートします。
まず、茶室への入り口です。普通の家のように、玄関があるわけではありま
せん。
この入口の事を「にじり口」といいます。幅1尺9寸5分、約60㎝位です。
高さは2尺2寸5分ですから、65~70㎝位でしょうか。
とっても小さい入口ですね。
多分、私の巨体(身長:170㎝、体重:86kg、ウエスト:95㎝)では、き
っと入れるか不安です。
最も、偉い人専門に設けられた入口もあるのです。この入口の事を、「貴人
口」(きにんぐち)といいます。
中に入ると、目に付くのは、風炉(ふろ)です。ここで、お湯を沸かします。
周りを見渡すと、床の間があります。ひどく小さなスペースですが、床柱は
面皮柱(めんがわばしら)で、内面の柱や天井の縁は壁で隠されています。
この様式を「室床」(むろどこ)といいます。
畳が敷かれていますが、普通のものよりかなり小さいサイズです。この畳の
事を「台目畳」(だいめだたみ)といいます。
壁は土壁で、下地の格子状の竹を見せた窓があります。この窓を「下地窓」
(したじまど)といいます。そしてこの窓に引っかけておく障子を「掛け障
子」といいます。天井は、傾斜天井と平天井を組み合わせた掛け込み天井で
す。よしず貼り天井なども考案されています。私はこの天井が気に入ってい
ます。
最後に、茶を飲んでにじり口から、よっこら出たところに雪隠(せっちん)
やつくばい、石灯篭などが配されました。
雪隠とは便所の事で、つくばいは手を洗う場所のことです。
皆さん、思ったより一杯のエレメントが、この小さな空間を構成しているこ
とに驚かされますよね。

今日はここまで。
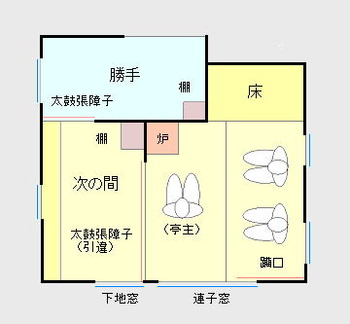
Posted by massan&junjun at 09:26│Comments(2)
この記事へのコメント
にじり口から出入りすれば 秀吉だって
頭を下げなければいけない・・・
すごいアイデアだと思います
頭を下げなければいけない・・・
すごいアイデアだと思います
Posted by hanabusa at 2009年07月05日 21:15
at 2009年07月05日 21:15
 at 2009年07月05日 21:15
at 2009年07月05日 21:15コメントありがとうございます。
昔の人の知恵、恐るべしですね。
しかし、利休は己の知恵を自己破滅に導いてしまいました。
もう少し、別のやり方があったと思うのは私だけでしょうか。
昔の人の知恵、恐るべしですね。
しかし、利休は己の知恵を自己破滅に導いてしまいました。
もう少し、別のやり方があったと思うのは私だけでしょうか。
Posted by まっさん at 2009年07月05日 21:57


